2025年5月、これまで9千人の人員削減を発表している日産自動車が、追加で国内外合わせて1万人の人員削減を実施するという方針を固め、大きな注目を集めています。
実は、日産のリストラは今回が初めてではありません。
過去にも何度も人員削減を行ってきており、そのたびに話題になってきました。
では、なぜ日産は繰り返しリストラを行うのか?
どんな人が対象になるのか?
退職金はちゃんともらえるのか?
この記事では、そんな疑問に答えながら、過去の動きや今回の背景をわかりやすくまとめていきます。
日産のリストラ、なぜ繰り返されるのか
日産のリストラは、経営危機や業績悪化のたびに大規模に実施されてきました。
その背景には、1999年のルノーとの資本提携以降続く構造改革があります。
特に近年は、北米や中国での販売不振、EV市場での競争力低下、そして海外での生産能力の過剰といった構造的な課題が重なり、再び人員削減が避けられない状況に。
日産はこうした厳しい環境の中で、収益性の回復と企業体質の強化を図るため、大規模なリストラに踏み切らざるを得ない状況にあるのです。
日産過去のリストラ歴史まとめ
日産自動車がこれまでに実施してきたリストラ事例がこちらです。
| 年代 | 主な内容 | 規模・対象 | 背景・理由 |
| 1990年代 | 工場閉鎖・人員削減 | 座間工場など | バブル崩壊後の経営危機 |
| 1999–2001年 | 日産リバイバルプラン | 5工場閉鎖・ 2.1万人削減 | 累積赤字・有利子負債2兆円超 |
| 2019年 | 大規模人員削減 | 1万2500人規模 | 営業利益98.5%減など業績悪化 |
| 2024–2025年 | グローバルリストラ・早期退職募集 | 9000人削減 +国内外1万人削減 | EVシフト遅れ、中国市場苦戦、業績低迷 |
1990年代:バブル崩壊後の経営危機と初期のリストラ
バブル経済崩壊により業績が悪化し、日産は経営危機に陥りました。
辻義文社長のもとで座間工場を閉鎖するなど、初めて本格的な人員削減に踏み切りました。
1999〜2001年:ルノー資本提携と「日産リバイバルプラン」
ルノーとの資本提携を契機に、カルロス・ゴーン氏が主導する「日産リバイバルプラン」が始動。
国内5工場を閉鎖し、2万1千人の人員削減を実施。
系列解体とコストカットで短期黒字化を達成しました。
2019年:再びの業績悪化による大規模リストラ
ゴーン体制終焉後、西川廣人社長のもとで再び業績が悪化。
営業利益が約98.5%減となり、1万2500人の削減を発表。
回復が期待された中での逆風となりました。
2024〜2025年:EV戦略遅れとグローバル再編
日産は2024年11月に9000人の人員削減を発表しましたが、2025年5月にはさらに1万人超を追加し、全従業員の約15%にあたる約2万人を削減する方針を固めました。
北米・中国での販売不振や、2025年3月期に最大7500億円の赤字が見込まれるなど、業績悪化が背景にあります。
国内外の拠点が対象となり、一部工場の閉鎖や生産体制の再編も含まれます。
生産能力は約100万台分、固定費は3000億円規模を削減予定。
経営再建に向けて抜本的な改革が進められています。
人員削減の対象と傾向――誰がリストラされやすいのか?
日産が行ってきた人員削減は、特定の地域や部門に限らず、全社的・グローバル規模で広がっています。
特に販売不振が続く北米や中国などの拠点では、大規模な削減が相次いでおり、例えばタイでは約1,000人が削減・配置転換の対象に。
米国でも数百人規模で早期退職が進められました。
削減の対象は製造現場にとどまらず、営業、事務、管理、企画といった間接部門にも及んでいます。
また、正社員だけでなく、契約社員や期間従業員など、雇用形態に関わらず幅広く対象となっているのも特徴です。
人員削減の選定基準とは?
日産はリストラの選定基準を公表していませんが、過去の動向からいくつかの方針が見えてきます。
まず早期・希望退職では、年齢や勤続年数の長い社員が主な対象で、退職金の上乗せによる自主的な退職が促されます。
また、業績や生産性が低下した拠点や部門も優先される傾向があります。
さらに、北米やアジアなど競争力の低下した海外拠点では再編が進み、大規模な人員削減が行われています。
非正規社員の契約終了も調整手段の一つです。
日産のこれまでの人員削減における退職金・優遇制度の実態
日産では過去の人員削減の際、「早期退職優遇制度」が複数回導入されてきました。
対象は主に45歳以上の一般社員で、管理職は除外されるケースが多く見られます。
2000年代の大規模リストラでは約1万2000人を対象に期限付きで募集されました。
優遇内容としては、通常の退職金に加えて割増退職金が支給されるほか、再就職支援やキャリアカウンセリングなども提供。
割増額は公表されていませんが、業界水準では数百万円から数千万円規模の加算が一般的です。
近年も、国内の事務系部門を中心に数百人規模の募集が計画されています。
役員や幹部の退職金については、経営責任を考慮して減額されるケースもあり、西川前CEOの退職手当は大幅に削減されました。
まとめ
日産はこれまで、1990年代の経営危機や1999年のルノー提携を契機に、幾度も大規模なリストラを実施してきました。
特に2024〜2025年には、世界で約2万人、全従業員の約15%におよぶ削減が進められ、北米・中国などの販売不振拠点や事務部門を中心に早期退職や配置転換が行われています。
日産の相次ぐリストラは、経営再建やグローバル競争を勝ち抜くために避けられない選択かもしれません。
しかし、現場で働く従業員にとっては、突然の退職勧奨や職場の縮小は生活や将来に直結する深刻な問題です。
「企業の都合」で片付けられない現実がそこにあります。
企業が変革を進める中でも、働く人々の尊厳や生活を守る視点を忘れてはならないと感じさせられます。
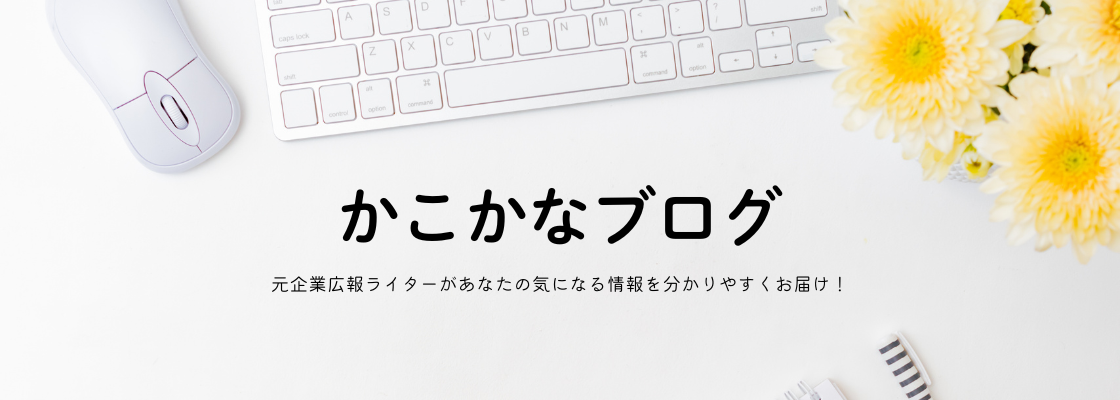
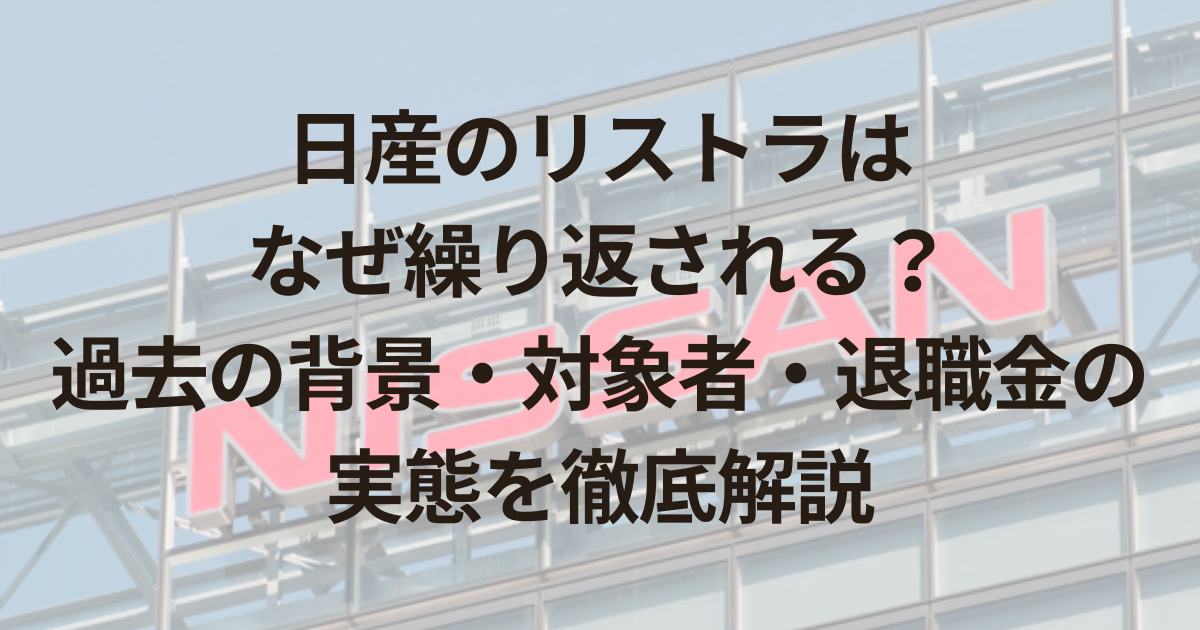
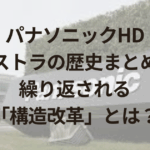
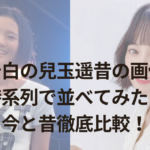

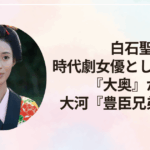


コメント