2025年秋の自民党総裁選で見事に当選を果たした高市早苗さん。
「ついに日本初の女性総理誕生か!」とニュースでも大きく報じられましたよね。
ところがその直後、「高市さん、総理になれないかもしれない」という予想外の展開が広がっています。
「え、総裁に当選したのになんで?」
「もう総理じゃないの?」と、ちょっと混乱している人も多いのではないでしょうか。
実は、“自民党総裁=総理大臣”ではないんです。
総理になるには、国会で過半数の支持を得る必要があり、今の高市さんはその壁にぶつかっています。
この記事では、そんな高市早苗さんが「総理になれないかもしれない」3つの理由を、できるだけわかりやすく解説していきます。
はじめに:なぜ「総裁=総理」じゃないの?
多くの人が「自民党総裁に当選したら、そのまま総理大臣になる」と思いがちですが、実はそう単純ではありません。
総理大臣は、「国会の首相指名選挙」で国会議員の過半数の支持を得た人が選ばれる仕組みになっています。
つまり、自民党の総裁になっても、国会で多数派を取れなければ総理にはなれないということなんです。
これまでは、自民党が公明党と連立を組んで“与党多数”を維持してきたため、総裁=総理という流れが自然にできていました。
しかし今回、高市早苗さんの場合は、その前提が大きく崩れています。
公明党が連立を離脱し、自民党が単独で過半数を割り込んだことで、
「国会での首相指名選挙に勝てない=総理に就任できない」という前代未聞の状況が生まれているのです。
次の章では、そんな“高市総理誕生が遠のいた”主な理由を3つに分けて、順番に見ていきましょう。
公明党が連立離脱!支えを失った自民党
高市早苗さんの“総理就任が危うくなった”最大のきっかけが、公明党の連立離脱です。
2025年10月、公明党は「高市体制では協力できない」として、自民党との26年続いた連立関係を解消しました。
このニュースは政界に衝撃を与え、「まさかここで手を切るとは…」という声も上がりました。
公明党が離脱を決めた背景には、いくつかの理由があります。
- 自民党の「政治とカネ」問題への対応が甘かったこと
- 高市氏の保守色が強く、外交・安全保障・歴史認識などで価値観が合わなかったこと
- 靖国参拝など、宗教的・思想的に受け入れがたい政策姿勢

特に公明党の支持母体である創価学会の一部からは、「高市政権では信頼できない」との声が強まっていたとされます。
この連立離脱は単なる“政治的立場の違い”ではなく、国会運営そのものを揺るがす事態に発展しました。
なぜなら、公明党は選挙で自民党を支える“組織票”の柱であり、国会でも安定多数を保つ要となっていたからです。
その支えを失った今、自民党は単独では法案を通すのも難しい状態に。
つまり、「高市政権」が発足したとしても、国会で何も進まない可能性が高いのです。
こうして、長年続いた“自民+公明=与党多数”という構図が崩れたことで、高市早苗さんの総理就任への道は一気に険しくなりました。
国会で過半数割れ、首相指名選挙で勝てない?
公明党が連立を離脱したことで、自民党は国会での“数の力”を一気に失いました。
衆議院の議席数は、自民党が約199、公明党が21。
この21議席が抜けたことで、過半数の233議席に届かなくなってしまったのです。
総理大臣は、国会で行われる「首相指名選挙」で決まります。
ここでは各党の議員が、自分の党の候補者の名前を書いて投票し、過半数を取った人が総理になるというルール。
つまり、単純に“数の勝負”なんです。
これまでは「与党(自民+公明)で多数派」だったため、自民党総裁がそのまま総理に就任できました。
しかし今は違います。
高市さんに投票してくれるのは、自民党の議員だけ。
一方で、野党側(立憲民主党・日本維新の会・国民民主党など)が候補を一本化すれば、数の上で高市さんを上回る可能性が出てきます。
たとえば、
- 立憲民主+維新+国民民主などがまとまれば、230議席超を獲得できる見込み。
- もし一票差でも上回られれば、総理の座は他の候補に渡ってしまうのです。
つまり高市早苗さんは、自民党総裁という立場にありながら、国会で「自分を総理に指名してくれる人」が足りないという前代未聞の状態に陥っているわけです。
この“数の論理”こそが、総理就任を阻む最大の壁になっています。
新たな連立相手探しも難航
公明党が抜けた今、自民党は“数の上での過半数”を取り戻すために、新しいパートナー探しに奔走しています。
候補として名前が挙がっているのが、国民民主党と日本維新の会。
どちらも比較的政策が近く、過去にも自民と協力関係を築いたことがあります。
しかし、現実はそう簡単ではありません。
まず、国民民主党。
この党は労働組合の全国組織「連合(日本労働組合総連合会)」の支援を受けています。
その連合が「自民党との連立は絶対に認めない」という強い姿勢を示しており、党としても簡単に与党入りはできない状況です。
さらに、エネルギー政策や社会保障などの分野でも、自民と意見が大きく食い違っています。
一方の日本維新の会も、「大阪副首都構想」など独自の地方改革路線を掲げており、自民との政策調整は難航。
維新側は閣僚ポストの配分や政策協定の明文化など、具体的な条件を提示していますが、どちらも譲らず協議は長期化しています。
その結果、どの党も“連立入り”には慎重または否定的。
自民党が単独で国会を乗り切るには、法案や予算の可決でも野党側に頭を下げざるを得ず、非常に不安定な状態です。
今後、部分的な「政策協定」や「法案ごとの協力」にとどまる可能性も高く、
高市政権の誕生はおろか、“政権を安定して運営できる見通し”すら立っていません。
まさに今、自民党は「連立の再構築」という最大の難題に直面しているのです。
まとめ:高市総裁=総理ではない“壁”の正体
今回の一連の流れを見てみると、「総裁に当選したのになぜ総理になれないの?」という疑問の答えが少し見えてきます。
高市早苗さんが総理になれない可能性が高まっているのは、
1️⃣ 公明党が連立を離脱したこと、
2️⃣ 国会で過半数を失ったこと、
3️⃣ 新たな連立相手を見つけられないこと——。
この3つが同時に起きているからです。
自民党単独では、国会の多数派を維持できず、首相指名選挙で過半数を取ることができません。
つまり、高市さんがどれだけ総裁として支持を集めても、「国会で選ばれなければ総理にはなれない」という現実に直面しているのです。
これまでの日本政治では、自民党総裁=総理大臣が“当たり前”のように続いてきました。
しかし今回、その構図が初めて崩れつつあります。
高市早苗さんの手腕や政治信念は多くの注目を集めていますが、政権を支える「数の力」なしには前に進めません。
今後、どの党とどんな形で手を組むのか——。
その一手が、日本の政治の流れを大きく変える分岐点になりそうです。
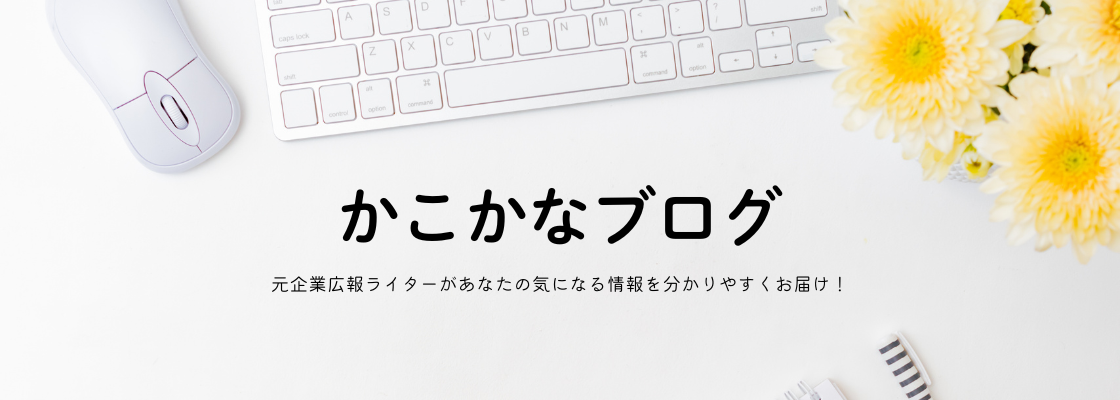
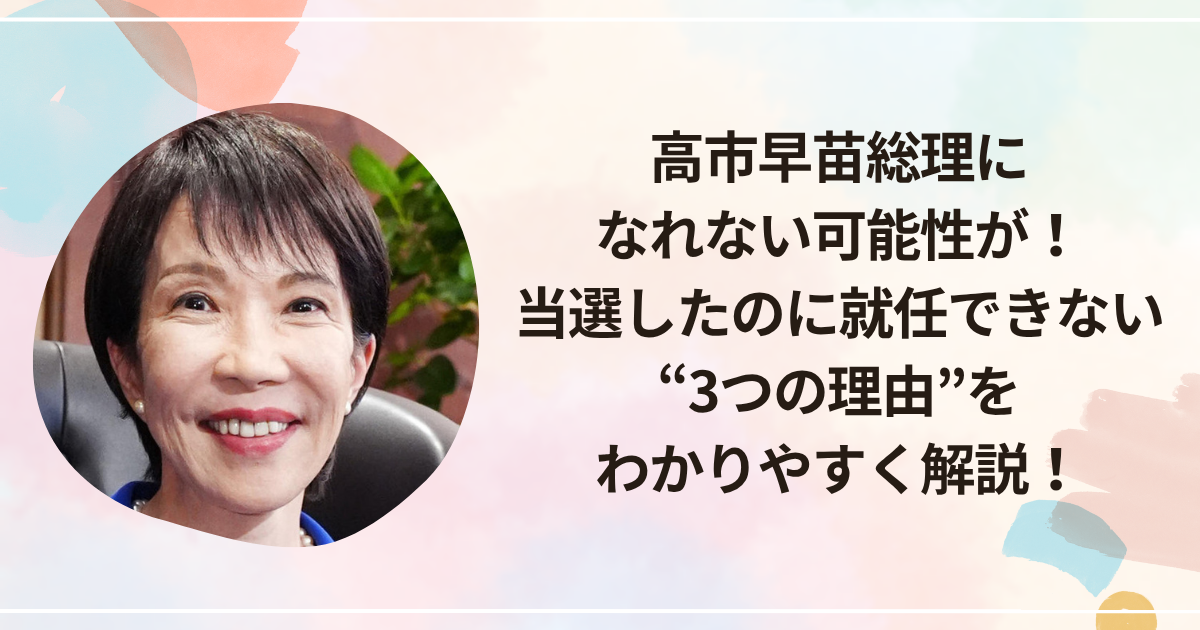
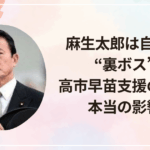
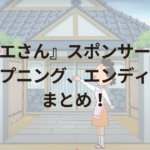
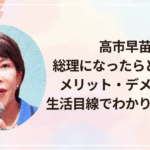
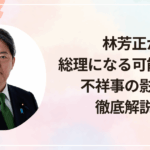
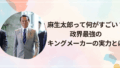
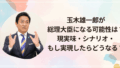
コメント